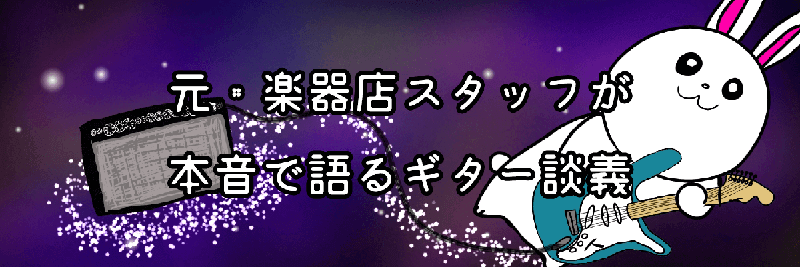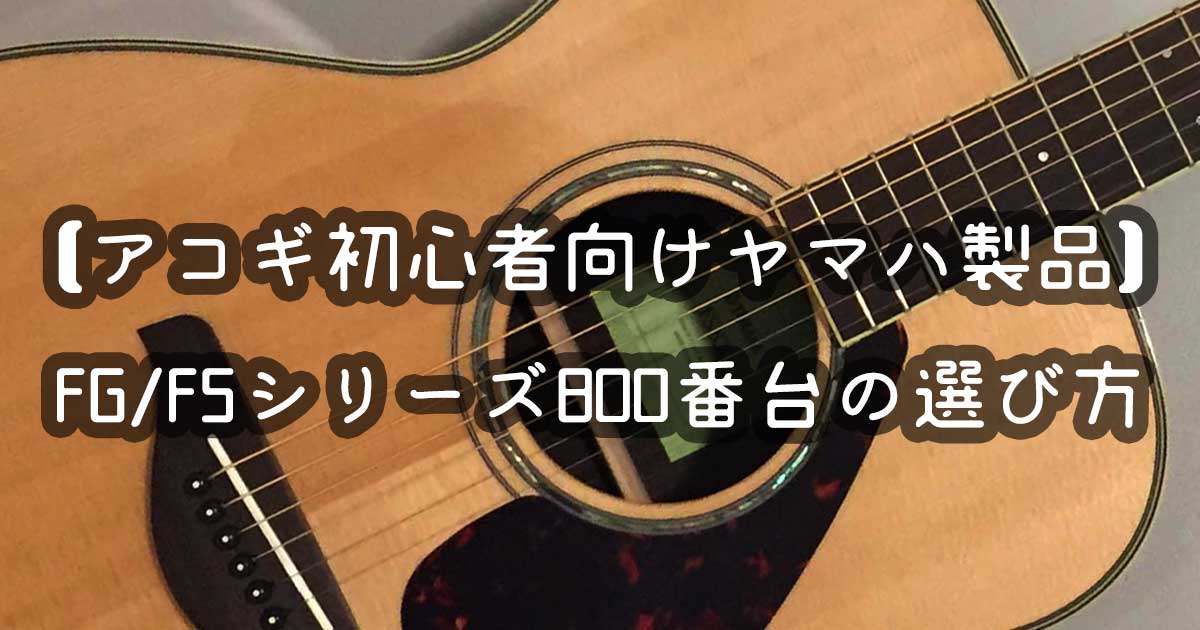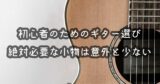はじめてのアコギ選びでは「そもそも予算の目安を絞り込めない。ギターのメーカーの見当がつかない、モデルやデザインの決め方が全然分からない」ところからスタートする方がほとんど。
そんなときに楽器店員が比較基準として紹介する定番かつ、最初におすすめしやすいアコギの代表格がヤマハFG800/FS800番台シリーズです。
ただし、じつはFG800/FS800番台シリーズのなかに、さらに全11機種のラインナップが展開されています。
そこで型番の数字部分(800/820/830/840/850)によって仕様が異なるのですが、ギター初心者の方には少々違いが分かりにくいんです。

2024年1月時点のメーカー希望小売価格は税込33,000円~税込49,500円だよ。
本記事では「ヤマハFG/FS800番台のアコギについて特徴や違い」を簡単に比較できるように、ステップ形式で選び方を解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
ステップ1:FGシェイプとFSシェイプでボディ形状の好みを選ぶ
まず、ヤマハのアコギで多数の型番に含まれている「FG/FSの違い」から解説していきましょう。
モデル名の頭に付いている「FG」と「FS」でギター形状(シェイプ)が異なるので製品画像を並べてみます。
下画像はヤマハの同シリーズで最も安い価格設定のFG800/FS800モデル。
どこを見比べるのが分かりやすいかというとボディ中央付近です。FGシリーズとFSシリーズで楽器本体の「くびれ具合」が違うんですよね。
各シェイプの違いを説明するときの常套句になっているのが、
- 「コードストローク派にはボディが大きいFG(エフジー)シリーズ」
- 「フィンガーピッキングやソロギター派にはボディが小さいFS(エフエス)シリーズ」
ただ、それを聞いて「???」となりそうであれば、今の段階であまり気にしなくて大丈夫です。
なぜなら最初のアコギであれば色々な演奏スタイルに挑戦することになるし、「自分がどういう奏法にハマるか」は少し先にならないと分からないからです。

それぞれ音量も違いがあるけど、ビギナーの人が想像しているほど大きな差ではないよ。
少しだけ噛み砕くと、音色の性格(キャラクター)に関しては「楽器の大きさから影響を受けるところ」があって、力強いサウンドが出しやすいのはFG、繊細なサウンドが出しやすいのはFSという傾向になります。
FGとFSのどちらが好みかは直感で選んで問題ないのですが、楽器の抱えやすさと弦の押さえやすさではFSモデルにおすすめ機種として軍配が上がるでしょう。
それは主に「ボディの厚みが少し薄い」のと、ネックの弦長が短いことで「同じ太さの弦でもハリが弱くなる特徴」によるもの。
かといって、誤解してもらいたくない部分で「FGモデルが特段弾きにくいというわけではない」です。
いずれも極端にギターのサイズやデザインが違うわけではなく、FGボディとFSボディを比較するとわずか1センチ~3センチの差。
あくまで慣れの側面が大きいので、今の段階では「どちらかといえばFSモデルが弾きやすいかも…」といったニュアンスだと捉えていただければと思います。
ヤマハFG/FSのサイズを比較すると、弦長は650mm/634mm、全長は1,038mm/1,021mm、ボディ長は505mm/497mmです。

ショルダー付近・くびれ部分・最大幅もカタログに記載されていて、FGモデル は292mm×268mm×412mm、FSモデルは279mm×233mm×380mmとなっています。
ステップ2:ナチュラル色なら800~850番の全機種を候補にできる
さて、ステップ1の内容をおさえたら、今度は「FG800とFS800それぞれの系統のバリエーション」を選ぶことになります。
アコースティックギターとして最もオーソドックスなのがナチュラルカラー。実際シリーズの全機種にラインナップされています。
価格によって「サイドバック(側板・裏板)の木材や装飾に違い」があるので以下で順番に見てみます。
FG820とFS820からはマホガニーボディでバインディングが付く
ヤマハのFG820とFS820の製品写真は下記をご覧ください。「FS820とFG820の違い」はまずボディ形状でチェックするんでしたね。
ボディ中央付近のくびれが強いほうがFS820です。
「ステップ1」で見た800シリーズと比較して、「FG800とFG820の違い、FS800とFS820の違い」の観点で解説すると、ネックの指板(左手で握る部分)にバインディング(縁取り)が付いているのが分かるでしょうか。
バインディングがあることで入門モデル特有の「安っぽさ」は払拭され、遠目で見たときにも外観のメリハリが出ています。

ボディの木材もナトー/オクメ材からマホガニー材にアップグレードされているんだよ。
FG830とFS830はローズウッドボディの上品な音色で装飾も綺麗
続いて下記はヤマハのFG830とFS830というモデル。
「FG830とFG820の違いは?」「FS830とFS820はどっちがいい?」など、楽器店の店頭でよく聞かれる質問です。
820については前項で紹介しましたが、830シリーズは「ローズウッド材で製作されたボディ」による明瞭で深みのあるサウンドが特筆すべきところ。
この二機種は800番台シリーズの中でも、とりわけコスパの高さに定評があって人気ランキング常連のおすすめモデルになっています。
さらにFG830/FS830だと、820シリーズと異なり(指板だけでなく)ギターのヘッド周囲までバインディングが施されているのに気付きましたか?

第一印象で目立つサウンドホール(ボディ中央部)の装飾が華やかになっていることも、かっこいいポイントなのでチェックしてみてください。
FG850とFS850はマホガニートップでブラウン系の渋い雰囲気
そして、ステップ2の最後。FG850とFS850だけはボディトップが(スプルース材ではなく)マホガニー材を採用したモデルになっています。
同じ「ナチュラル・フィニッシュ」でもブラウン系の色味なので、すぐに見分けが付きますね。
木のぬくもりを感じさせる「家具のように落ち着いたウッディな雰囲気」が渋いので、FG850とFS850は他機種よりレトロな佇まいに感じる方もいるかもしれません。
こういった木材の種類は音色面にも影響してくるところで、中低音域のふくよかさが目立つ印象の製品となっています。
FGシェイプのみ「FG840」というフレイムメイプル材で製作された仕様があります。裏板・側板に美しい杢目(もくめ)が入っており、サウンドも明るく硬質な傾向です。※「FS840」はありません。
ステップ3:豊富なカラーから選ぶならFG820とFS820に注目しよう
いよいよステップ3ですが、ここはナチュラル以外のカラーで選びたい場合にご覧ください。自然とモデルが絞り込めます。
端的には「ステップ2」でチェックしたFG820/FS820(マホガニーボディ)もしくはFG830/FS830(ローズウッドボディ)が選択肢となってくるでしょう。
830シリーズは「サンバースト」系のグラデーションに留まりますが、ヤマハFG820/FS820モデルは一番カラーオプションの多いロングセラーモデルです。
つまり「FS820とFS830はどっちがいい?」「FG820とFG830はどっちがいい?」という質問に回答するなら、「スペックに関しては830が上位、カラバリを優先するなら820のほうが豊富」という説明になります。
たとえば、FG820の「ブラック、サンセットブルー」や、FS820の「ブラック、ルビーレッド、ターコイズ」が830のほうでは選べない選択肢ですね。
なおFG820/FS820には、もともと前身となるモデルがあって、2016年3月にアップデートされた経緯があります。もう8年も経ちますが、アコギ初心者向けの定番で一向に人気が衰える気配がないですね。
年間を通して品薄になりがちですが、ボディシェイプが違うと、同系色でもイメージが少し変わってくるので各製品のバリエーションを見比べてみましょう。
まとめ
以上、できるだけシンプルにまとめてみましたが候補は定まってきたでしょうか。
ヤマハFG/FS800~FG/FS850のアコースティックギターは、共通してボディトップに単板(たんばん)の木材を使用しています。

その表板を支えている力木は、スキャロップド・ブレーシングといって、優れた音響特性と耐久性を両立すべくヤマハが独自研究を重ねてきたものです。
「中低域のふくよかさ、きらびやかな倍音成分」が心地良く、演奏者のタッチによる強弱をしっかり反映してくれるのが大きな魅力。

ネック接合部やブリッジ形状も、YAMAHAで培われた長年のノウハウが活きているところだね。
同価格帯のアコギで比較したときの「弾きやすさ」はもちろん、「このくらい反応が良いギターだと上達も早いのでは?」というのが各方面で高評価を獲得している理由のひとつでしょう。
今回ご紹介したモデルごとの音色の違いは、「ヤマハの楽譜出版」公式Youtubeチャンネル下記動画で聞き比べできます。
「ギター本体だけでなく、アクセサリーもセットで準備しなくちゃ…」という方には下記で解説してあります。
以上、最後までご覧いただきありがとうございました!